小林 眞一郎 ou2株式会社 常務取締役 二級FP技能士

2025/03/18(火)
土地探しをしていると、不動産情報に「要セットバック」や「私道負担あり」と記載されていることがあります。
あなたはセットバックと私道負担の違いを知っていますか?
そこでこの記事では、セットバックと私道負担についてわかりやすく解説します。セットバックの費用や所有権、セットバックが必要な土地を購入するときの注意点もわかるので、ぜひ最後までご覧下さい。

まずは「セットバック」、「私道負担」の意味と違いを、わかりやすく解説します。土地探しで不動産情報を見る際の参考にしてみてください。
こちらの表ではセットバックと私道負担の違いを書いています。
詳しくは以下にて説明をしているので確認してみてください。
| 項目 | セットバック | 私道負担 |
| 発生要因 | 建築基準法による道路後退義務 | 公道に接しない敷地の通行権確保 |
| 適用対象 | 幅4m未満の道路に接する土地 | 私道を含む土地(旗竿地など) |
| 所有権 | 変わらず所有者に帰属 | 道路の持分を所有することが多い |
| 課税対象 | 固定資産税が課税されるケースあり | 持分がある場合、固定資産税が発生 |
| 管理責任 | 原則、所有者の管理 | 所有者または共有者による管理 |
ここからは、セットバックの定義や特徴と必要なケースについて解説していきます。
「セットバック」を簡単に言うと、「幅4m未満の道路があるとき、その道路に接している土地を敷地側に後退させて、道路幅を4m以上にしましょう」という決まりごとです。
土地を後退させてまで道路幅を4mにする理由は、建築基準法で「道路=4m以上」と決まっているからです(建築基準法42条)。公道、私道どちらも、幅4m以上を確保する必要があります。
ですが、古くからある土地には4m未満の道路がたくさんあります。そのため、「既存の建物があるうちはそのままでOK、建て替えの際に必ずセットバックをする」と定められています。
※セットバックした部分の土地の所有権については、後ほどQ&Aで解説します。
セットバックが必要なケース
内見や購入を検討している土地にセットバックが必要な場合は、基本的に「道路の中心から自分の土地までの距離を2m以上確保する必要がある」と考えておいて下さい。
(法律上の例外もありますが、ここでは割愛します)
幅員4m未満の道路に接する土地では、、建築時に一定部分を道路用地として確保するセットバックが必要なことには注意しましょう。
セットバック部分の所有権と固定資産税
セットバックした部分の土地所有権は引き続き維持されますが、建築物や構造物を設置することはできません。これは、将来的な道路拡幅や安全性の確保を目的としているためです。
また、セットバック部分の固定資産税については、原則として課税対象となります。
しかし、一部の自治体では非課税措置を講じているケースもあります。自治体によって対応が異なるため、セットバックが必要な土地を所有している場合は、事前に固定資産税の取り扱いについて事前に確認しておくことが重要です。
特に都市部では、セットバックによる土地利用の制約があるため、その影響を考慮した上で土地の活用を検討する必要があります。
セットバック部分の管理と利用
セットバック部分は将来的に道路として利用されることを前提としていますが、必ずしも自治体が管理するとは限りません。多くの場合、土地の所有権はそのまま所有者に残るため、自治体による道路整備が行われない限り、管理や維持は所有者の責任となります。
そのため、セットバック部分の清掃や雑草の除去、舗装の補修などは基本的に所有者が対応する必要があります。特に、雨水の排水や道路の安全性に関わる部分は、適切に管理しないと近隣住民とのトラブルにつながることもあります。自治体によっては、一定の条件を満たすことで管理を引き継いでくれる場合もあるため、事前に確認しておくことが重要。
私道負担の定義
私道負担とは、個人の所有地に含まれる私道部分を指します。この私道は、敷地の一部として所有者が単独で持つ場合や、近隣の住民と共有する場合があります。特に、建築基準法に基づく接道義務を満たすために、敷地の一部を私道として利用し、道路幅を4メートル以上にすることがよく見られます。これにより、建物の建設や改築が可能となります。私道負担は、不動産の価値や利用条件に影響を与えるため、購入や売却の際には注意が必要です。
私道負担が必要なケース
私道負担が必要となるケースは、主に建物を建築する際に接道義務を満たすためや、通行・インフラ整備のために発生します。例えば、公道に接していない土地に建物を建てる場合、道路としての機能を確保するために一部の土地を私道として提供しなければならないことがあります。
また、複数の住宅が建つ分譲地では、共有の私道を設けるケースもあります。私道負担が発生すると、維持管理や修繕の費用を所有者が負担する必要があり、事前の確認が重要です。
私道負担部分の所有権と固定資産税
私道に関する固定資産税については、所有者により異なる負担が生じます。まず、地主が私道を所有している場合、固定資産税の納付義務は地主にあります。敷地をセットバックして私道を設けた場合も同様です。次に、私道が共有名義の場合、関係者はそれぞれの持ち分割合に応じて税金を支払う必要があります。また、分担して所有している場合には、それぞれが自分の所有部分に対して固定資産税を支払います。
さらに、私道の取得には不動産取得税がかかり、市街化区域内であれば都市計画税も課されます。相続した場合には相続税の対象となります。ただし、私道が自治体に申請され「公衆用道路」と認められた場合、固定資産税や都市計画税、不動産取得税が非課税となります。公衆用道路とは一般公衆が交通のために利用する道路のことを指し、登記簿謄本の地目に「公衆用道路」と記載されます。これに対し、認められない私道は地目が「宅地」となります。
土地の購入時には、売主の納税通知書を確認することが重要です。納税通知書には売主の所有する土地と建物の地番が記載されており、地番に「非課税」とあれば、その私道が公衆用道路として認められていることを示しています。これにより、将来の税金負担を正確に把握することが可能です。
私道負担部分の管理と利用
私道負担部分の管理と利用は、所有者がその責任を負います。管理面では、私道の陥没や舗装の亀裂などの問題が発生した場合、所有者が自己の費用で補修を行う必要があります。
また、メンテナンス費用も所有者が負担することが求められます。さらに、私道の状態が原因で事故が発生した場合、所有者が損害賠償責任を負うことが求められます。
私道は基本的に所有者の許可なしに利用することはできません。ただし、建築基準法上の道路として指定されている場合には、通行を禁止することは原則不可です。

セットバックが必要な理由は、主に3つです。
セットバックは隣家にとっても安全上必要で、「スムーズに出入りできる道路に接している土地」という点から、土地の価値を上げることもできます。
でも実際には新しく建物を建設する際に、セットバック逃れをしている事例も多数あります。セットバック逃れをすると、以下のような問題が発生します。
土地を安全&便利に活用するため、セットバックは必要です。

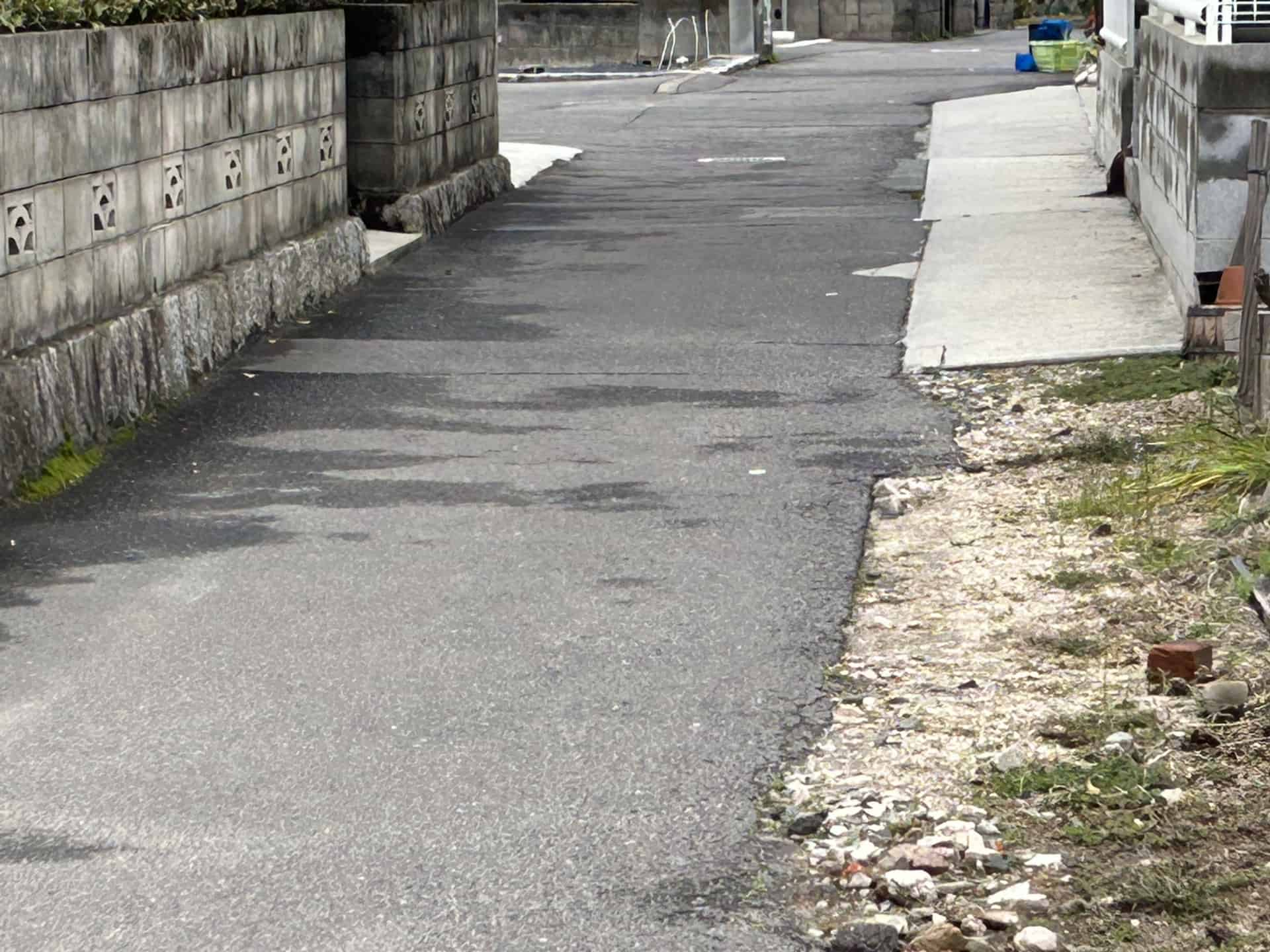
セットバックや私道負担にはいくつかの注意点があります。
まず、セットバックした土地は道路として扱われるため、個人の自由な使用は制限がかかるのです。この土地は消防車が通行できるようにする必要があり、建ぺい率や容積率の計算から除外されます。管理責任は土地所有者にあるため、草木の手入れや清掃を定期的に行う必要があります。もし事故やトラブルが発生した場合、基本的に所有者が責任を負ってしまう可能性も。また、セットバックした土地の固定資産税は非課税ですが、非課税適用を受けるには自分で申請することが必要です。
対策としては、まず固定資産税の非課税適用を受けるために、各自治体の建築指導課や道路管理課に問い合わせて確認することが重要です。土地の管理責任を果たすために、定期的な清掃や草木の手入れを怠らないようにしましょう。
また、インフラ整備の工事範囲によっては近隣住民や関係者の許可が必要になることがあるため、日頃から良好な関係を築いておくことが大切です。これらの点に注意し、適切な対策を講じることで、セットバックや私道負担に関する問題を未然に防ぐことができます。
土地購入時に意識すべきチェックポイントは以下の2点です。
セットバック部分は原則として固定資産税の課税対象となりますが、一部の自治体では非課税措置があるため事前に確認が必要です。また、私道部分の固定資産税も非課税措置が適用される場合があるため、土地購入時にチェックしておきましょう。
私道負担がある場合は、自分が単独所有なのか、複数人で共有しているのか、または地主が所有しているのかをチェックしておきましょう。
トラブルを防ぐためのポイントは以下の2点です。
セットバックや私道負担の範囲をしっかり確認し、登記簿や測量図と実際の土地の状態が完全に一致しているかをチェックしましょう。隣地との境界が曖昧な場合、後々のトラブルの原因になります。
私道がある場合、舗装や排水設備の管理責任が誰にあるのかを確認しましょう。共有私道の場合は、トラブルを防ぐために、他の所有者と管理費用をどのように分担するのか事前に話し合いをしておくことが大切です。

セットバックについて、5つのよくある疑問をまとめました。
セットバックした土地の所有権については、自治体(都道府県、市区町村)によって取り扱いが違います。
例)
セットバックに関与しない自治体、積極的にセットバックに協力する自治体があるので、各自治体の建築に関する部署(建築安全課 等)問い合わせをおすすめします。
セットバックした土地の舗装についても、自治体によって取り扱いが違います。土地所有者が無料利用承諾、寄付、整備承諾をした場合は、自治体が費用負担をして舗装するのが一般的です。
ただし自治体が舗装負担をする場合でも、土地所有者には以下のような負担があります。
撤去費用等を補助してくれる自治体もあるので、こちらも問い合わせてみるのがおすすめです。
セットバック前の道路に電柱がある場合、セットバック後は電柱が道路の途中にあるようなかたちになってしまいます。
自治体がセットバック後の舗装等をしない場合は、土地所有者がNTT or 電力会社に移設を依頼しましょう。
自治体が整備をする場合は、手続き前に移設の依頼もしておくのがおすすめです。
また電柱移設費用については、状況や電力会社によって取り扱いが違います(無償、費用の半分を負担など)。
必ず「セットバックによる移設」と伝えた上で、費用等を確認して下さい。
セットバックした土地には、固定資産税がかかりません(非課税)。ただし「非課税になる要件がある」&「市区町村に届け出が必要」です。
固定資産税が非課税になる要件
要件は「セットバックをしたことで4m以上の道路が確保されていること」、「誰もが使える道路として機能していること」です。
草花のプランターを置いている等は要件を満たさなくなるため、注意して下さい。
市町村への届出
固定資産税の非課税申告書、土地の位置がわかる図などが必要です。必要書類を確認して、確実に届出をして下さい。
固定資産税の要件に該当していても、土地所有者が届け出をしない限り非課税になりません。「前所有者が届け出をせずに固定資産税を払い続けていた」というケースもあるため、土地購入時には状況確認が必須です。
固定資産税の不明点についての問い合わせ先は、市区町村の固定資産税課です。
セットバックした土地は道路なので、自由に使ません。門扉のような道路に固定する設備だけでなく、花壇、駐車場、駐輪場としても使えないことを、覚えておきましょう。
所有権を持っている場合は「自分の土地なのになぜ使えないの?」と考えてしまいますが、前述した「安全上の理由等で近隣全体にとって必要な土地」と割り切る必要があります。

ここまで、セットバックと私道負担の違いについて説明してきました。
セットバックは道路幅が4m未満の場合に敷地の一部を後退させて道路を4m以上に確保する制度で、私道負担は個人の所有地に含まれる私道部分を指します。
土地購入の際は自治体による非課税措置の有無を確認し、所有者や管理責任を明確にしておくことが重要です。特にトラブルを事前に防ぐためには境界線と持分を正確に把握し、管理ルールやメンテナンス費用の分担方法を共有しておくことが重要です。
また、土地活用について疑問や不安がある場合は、M-LINEへご相談ください。土地の選定方法や、購入した土地に最適な土地活用方法をご提案いたします。