小林 眞一郎 ou2株式会社 常務取締役 二級FP技能士
アフターフォロー
0120-261-121
[受付時間]10:00-12:00/13:00-18:00
[営業日]月・火・木~土(祝日は除く)
[受付時間]10:00-12:00/13:00-18:00
[営業日]月・火・木~土(祝日は除く)

狭小地に住宅を建てる際に「駐車場を作りたい」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。しかし、狭小地で住宅と駐車場のスペースを確保するのは、なかなか難しいですよね。
しかし、狭い土地でも設計などの工夫によって、駐車場を確保できた事例も多くあります。例えば、ビルトインガレージを作って縦の空間を有効活用する方法などです。
ただ、狭い土地で駐車場を作る際は、あらゆる問題点について理解を深めておくことが大切です。
そこで本記事では、狭い土地に駐車場を作る際の問題点や、狭い土地に駐車場を作る際の工夫点について詳しく解説します。狭い土地に駐車場を作るか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

狭小地に建てた住宅でも、敷地内に駐車スペースを設けることは可能です。都市部では、来客用や自家用車の保管場所として駐車場のニーズが高く、限られた敷地を有効に使う工夫が求められます。
例えば1台分の駐車スペースであれば、ビルトインガレージや縦列駐車を採用して対応できる場合があります。建物の配置や間取りを調整することで、居住スペースを確保しつつ、車を停めるスペースも設計に組み込めるでしょう。
また、駐車場は建物を建てる必要がないため、比較的低コストで整備できるのも利点です。コンクリート舗装や簡易的な屋根だけでも、実用性のある駐車スペースをつくることが可能です。
土地の形が変形していても、車の出入りができる幅や奥行きが確保できれば活用できます。さらに、バイクや自転車用のスペースとして使うなど、用途の幅を持たせることもできます。
このように、狭い土地でも条件を整えれば、住宅と駐車スペースを両立させることは十分に可能です。
ちなみに家が建てられないような狭い土地を所有している場合は、コインパーキングといった土地活用方法も有効です。

狭い土地に駐車場を作る際は、以下の3つの問題点に注意しなければなりません。
狭い土地の駐車場は、車が停めにくい・出し入れしにくいなどの問題や、外構デザインの自由度が下がるなどの問題があります。一度駐車場の施工をしてしまうと、修正が難しいため、事前に駐車場の問題の事例について確認しておきましょう。
狭い土地に駐車場を作ると、荷物の出し入れがしにくいのが問題です。なぜなら、1台が停められるようギリギリのスペースで作られている場合が多く、荷物の出し入れをする際は家や車に当たらないように注意する必要があるからです。
また、人の乗り降りがしにくいのもよくある事例になります。ドアの開閉時に家や車に当たらないか心配な方は、スライドドアなどの車を検討しましょう。
もう1点注意したいのが、バックドアの開閉スペースです。バックドアを開ける際は、1mほど後方に空間が必要です。車1台分がギリギリで入るスペースの駐車場だと、路上駐車して荷物の出し入れを行わなければならず、周りの迷惑となる場合もあります。
このように、駐車場を作る際は車1台を停められるかで判断するのではなく、「乗降時」「荷物の出し入れ」「バックドアを開閉時」など実用的なシーンをイメージして設計することが大切です。
狭い土地に駐車場を作る際は、停め方によって確保するスペースが異なります。理由としては、駐車場を作る際は直角駐車・並列駐車・縦列駐車の3種類あり、それぞれ確保するスペースの向きや広さが異なるからです。
最も一般的な駐車場のタイプは、直角駐車です。道路に対して車を直角に停める方法で、駐車場が車の長さ以上の奥行きと、前面道路が幅4m以上ある場合の駐車方法となります。
並列駐車は、横向きに停める駐車方法です。直角駐車と比べて奥行きは必要なくなりますが、車が停めづらい・2台確保するのは難しいといった問題があります。
縦列駐車は、2台の横並びスペースがない場合、縦に2台の車を停めるスペースが作れます。しかし、奥の車の出し入れをする際は、道路側の車を動かさなければならないのがデメリットです。
また、軽自動車など比較的小さめの車を所有している方は、将来大きな車に買い替える予定がないかも検討ポイントです。軽自動車はスムーズに停めることができても、ファミリーカーでは使い勝手が悪い場合もあります。
車の買い替えなど、将来起こりうる様々な想定をして、駐車スペースの検討をしましょう。
狭い土地に駐車場を作ると、外構デザインの自由度が下がるのが問題点です。なぜならフェンスや塀などは、周りの見通しが悪くなる場合があり、車が停めにくくなる可能性があるためです。
狭い土地では、敷地が限られているため、駐車場として活用してしまうと理想の外構デザインができない可能性もあります。他にも、車の排気ガスなどが直接当たる場所は、植物などに悪い影響を与える可能性があるため花壇などを設置するのは難しいでしょう。
このように、狭い土地に駐車場をスペースを作ると、外構デザインの自由度が下がってしまうのが難点です。マイホームのエクステリアにはこだわりたいという方は、狭小地の外構デザインが得意な業者に相談してみるのも一つの方法です。

狭い土地に駐車場を作る際は、以下の5つの工夫点を参考にしましょう。
狭い土地に駐車場を作る際は、駐車場の設計を工夫するだけなく、ビルトインガレージにするなど住宅の設計を工夫する方法もあります。以下では、それぞれの工夫点について解説するので、様々な選択肢を検討しましょう。
狭い土地に駐車場を作る際は、ビルトインガレージにするのがおすすめです。ビルトインガレージとは、駐車できるスペースを住宅の1階部分に設け、シャッターやドアを設置したガレージのことです。
理由としては、駐車場のスペースがない場合でも、住宅部分に駐車場スペースを組み込むことが可能なため、土地を有効活用できます。また、車を雨や日差しから守ることができ、荷物の積み下ろしや人の乗り降りの際も雨に濡れる心配もありません。
ただし、ビルトインガレージは住宅の1階部分に空間を作ることになるため、耐震性などを高める施工が必要になります。そのため、一般的な建築費用よりも費用が高くなる可能性があることを理解しておきましょう。
また、ビルトインガレージの床面積によって、固定資産税が高くなる場合があります。しかし、ビルトインガレージは、「建物の延床面積の5分の1を限度として、容積率の計算から除外できる」という緩和特例が用意されているのがポイント。
そのため、固定資産税の負担を増やしたくない方は、ガレージ部分の床面積を建物の5分の1以下に設計すると良いでしょう。
狭い土地に駐車場を作るために、スキップフロア・ロフトを利用する方法もあります。なぜなら、住宅のデッドスペースを有効活用できるため、住宅の床面積を減らし、駐車場スペースを確保できる可能性があるからです。
スキップフロアとは、床の一部の高低差を設けて、空間を仕切る方法です。廊下などの空間が不要になるため、その分浮いたスペースを駐車場として活用できる可能性があるでしょう。
また、ロフトは、一部の部屋を二層式にした上部空間です。屋根裏のデッドスペースなどを活用でき、収納場所としたり、読書をするスペースとして活用したりできます。
駐車場を増やすために、ロフトなどの空間を利用し、住宅の設計を見直してみるのも1つの方法でしょう。
土地が旗竿地であれば、車路を隣地と共有する方法もあります。理由としては、隣地と土地を共有することで、駐車スペースの空間に余裕を持たせられるからです。
例えば、隣地との間にフェンスなどを作らず土地を共有すれば、車2台を余裕を持って駐車できます。隣地との間をフェンスなどで仕切ってしまうと、ドアが開けにくくなったり荷物の積み下ろしが面倒になったりします。
広さや形状にもよりますが、お隣さんとの関係性が良ければ土地を共有できないか相談してみましょう。ただし、共有する際は事前にルールなどを決定し、必ずルールを守ることが重要となります。
どうしても自宅に駐車場を作るスペースが足りない場合は、近辺で駐車場を見つける方法もおすすめです。無理に狭い土地に駐車場を作ろうとすると、使いにくかったり停めにくかったりして失敗するケースもあります。
近辺に月極駐車場などがあれば、車の出し入れなどに苦労する必要もなく、スムーズに駐車できます。コストがかかりますが、どちらが便利なのかを考え、近辺で駐車場を見つける方法も検討してみましょう。
狭小地に住宅を建てる際は、軽自動車にするもしくは車を持たないという選択肢も検討しましょう。なぜなら、生活しやすい環境の場合は、車自体が必要ない場合もあるからです。
例えば、駅やバス停が近くにあったり、スーパーや病院など生活がしやすい環境だったりする場合などが挙げられます。徒歩や公共交通機関などを活用して、生活に困らない場合は車を持たないという選択肢も1つの方法でしょう。
また、普通乗用車に乗っている場合は、軽自動車にすることで駐車スペースを確保できる場合があります。最近では、普通車でも小型な車も多いので、小さめの車種を選ぶのも1つの方法です。
小型な車や軽自動車は燃費もよくなり、ガソリン代や自動車税の負担も減らすことができるのでおすすめです。


狭い土地に駐車場を作る理想の広さは、どの車両も同じ広さではなく、自分の所有している自動車の大きさによって違います。理由としては、対象車両に対して最低限必要な長さ・幅員が、国土交通省の指針で定められているためです。
国土交通省で定められた駐車ますの長さ・幅員に関しては、以下の通りです。
| 対象車両 | 長さ | 幅員 |
|---|---|---|
| 軽自動車 | 3.6m | 2.0m |
| 小型乗用車 | 5.0m | 2.3m |
| 普通乗用車 | 6.0m | 2.5m |
つまり、上記の数値が駐車場をコンパクトに作るための最低限の広さとなります。狭い土地で駐車場を作る場合は、以下の目安を参考にしてみてください。
また、自分の車にぴったりの駐車場を作るためには、マイカーのサイズを確認する方法も1つの方法です。車のサイズは、車検証などで確認することができます。
一般的に運転席・助手席のドアを開けた時に必要な広さは、「車両の幅+60cm」だといわれています。そのため、助手席側・運転席側で両方ドアを開けても余裕がある駐車場を作りたいなら、幅員を車両の幅+120cm程度確保する必要があるのです。
バックドアをフルオープンした時のスペースは、バックドアの長さ+30cm程度を目安にすると良いでしょう。バックドアより30cm長く駐車場を作れば、余裕を持って開閉ができるようになります。
ただし、荷物の積み下ろしなどの頻度が多い方は、基本的な広さよりもゆとりを持った広さにするのがおすすめです。具体的には、以下のような場合は、一般的な駐車場よりも広く設計をした方が良いでしょう。

駐車場を設けたいと考えたとき、「どれくらい費用がかかるのか」「少しでも安く抑えるにはどうすればよいのか」と悩む方もいるでしょう。
ここでは、駐車場設置にかかる費用の目安を確認したうえで、コストを抑えるための具体的な方法を3つ紹介します。施工の種類別に費用感を整理しながら、無駄な出費を防ぐための考え方や工夫も併せて解説していきます。
駐車場をコンクリートで舗装する場合、1台分(約15㎡)で17万円〜23万円が相場です。2台分(約30㎡)なら、24万円〜30万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
コンクリートの平米単価は1㎡あたりおよそ8,000〜12,000円で、整地や型枠の設置、流し込み、養生などの工程が必要になります。そのため、材料費や人件費の高騰も影響しやすく、全体の工事費用は比較的高くなる傾向です。
コストを抑えたい場合は、タイヤの乗る部分だけをコンクリートで舗装し、その他は砂利や芝などを活用する方法が有効です。施工面積を減らすことで、費用を抑えつつ機能性も維持できます。
また、複数の業者から見積もりを取得して価格と内容を比較すれば、同じ工事内容でも10万円以上の差が出ることも。加えて、夏などの閑散期に依頼することで、割安に工事を依頼できる可能性もあります。
駐車スペースの快適性や防犯性を高めるために、カーポートやフェンス、門扉などを追加するケースも少なくありません。これらの設備にも費用がかかるため、予算内に収めるには工夫が必要です。
カーポートの設置費用は、車1台分で15万〜50万円程度が一般的ですが、屋根の素材や構造によっては40万〜100万円ほどになる場合もあります。
フェンスは、設置する長さや素材によって金額が大きく変わりますが、全体の相場は約30万〜60万円ほど。プライバシー確保のための目隠し機能を付けると、追加費用が発生することもあります。
門扉については、シンプルなデザインであれば15万〜20万円程度で設置可能ですが、凝った意匠や高級素材を選ぶと30万円程度が目安です。
コストを抑えるためには、複数の施工業者に見積もりを依頼して比較するのが基本です。また、DIYが可能なパーツを取り入れれば、人件費の削減にもつながります。さらに、施工時期を工夫し、閑散期に依頼することで、値引きやキャンペーンを活用できる可能性があります。
駐車場の設置では、DIYと外注のどちらを選ぶかによって、費用や手間に大きな違いが生まれます。どちらが自分にとって得かを見極めるためには、費用だけでなく、施工の難易度や所要時間も含めて比較することが重要です。
例えばDIYで砂利を敷く方法を選べば、1㎡あたり2,000円〜3,000円程度に抑えられ、大幅なコスト削減が可能です。施工範囲をタイヤが接地する部分だけに限定し、他のエリアは芝生や防草シートで対応すれば、さらに費用を抑えられます。
ただし、DIYは手間や技術が求められるため、「時間に余裕があるか」「施工に自信があるか」なども判断材料にすることが大切です。一方で、外注は費用がかかる分、仕上がりや耐久性に安心感があり、短期間で完成するというメリットがあります。
このように、予算・時間・仕上がりの希望に応じて、DIYと外注のメリット・デメリットを比較し、自分にとって最適な方法を選択することが、後悔のない駐車場づくりにつながります。

限られた敷地でも、工夫次第で快適に使える駐車スペースは実現可能です。都市部や狭小地など、スペースに制約がある土地でも、レイアウトを工夫することで使い勝手のよい駐車場をつくることができます。
ここでは、実際によく取り入れられている3つのレイアウト例を紹介します。
ビルトインガレージは、住宅の1階部分などに駐車スペースを組み込む設計で、敷地を無駄なく使えるのが大きなメリットです。建物の内部に車を収めるため、敷地全体に余裕がなくても駐車スペースを確保できます。
雨や風をしのげるため車の劣化を防ぎやすく、荷物の出し入れや移動も屋内で完結できる点が魅力です。加えて、防犯面でも安心感があります。都市部の狭小地では特に人気の高いレイアウトです。
土地の間口が狭くても、奥行きが確保できるなら、縦列駐車が有効です。1列に車を前後に並べて駐車するスタイルで、2台以上の車をスリムな敷地内に収めることができます。
手前の車を動かす手間はあるものの、スペース効率は非常に高く、特に長方形に近い土地での活用に適しています。住宅の側面や裏側に駐車スペースを設けるケースも多く見られます。
前面道路が狭かったり、土地の形が正方形でなかったりする場合には、斜め駐車が効果的です。車を斜めに配置することで、切り返しや車の出し入れがしやすくなり、スムーズに駐車できます。
見た目もすっきりと整いやすく、限られたスペースの中で快適な動線を確保したいときにおすすめです。角度を工夫することで、スペースの無駄も最小限に抑えることができます。

ここからは、狭い土地に駐車場を作る際に、よくある質問を紹介します。
狭い土地では、「狭い駐車場を広くしたい」といった声が多くあります。特に頻繁に自動車を利用する人にとって、駐車場が使いやすいかどうかが非常に重要となります。
狭い土地の駐車場作りに失敗しないためにも、ぜひよくある質問の内容についてもチェックしておきましょう。
狭い土地の駐車場を広くすることは可能です。狭い土地の駐車場を広くするには、家の設計を工夫する方法があります。
前述でも解説した通り、ビルトインガレージやスキップフロア・ロフトを活用する方法です。
駐車場を広くできる理由としては、狭い土地を有効活用するためです。ビルトインガレージでは、住宅の一階部分に駐車場を作るため、住居部分に駐車場を組み込むことができます。
スキップフロア・ロフトは、廊下や収納スペース等などの空間が不要になり、浮いたスペースを駐車場として活用できます。ただし、どちらの方法も建築費用が高くなる可能性もあるため、事前に色々な設計で見積もりを比較して検討しましょう。
駐車場の寸法は、法律で定められている訳ではありませんが、国土交通省の指針によって駐車ますの大きさが定められています。
前述でも紹介しましたが、国土交通省で定められた駐車ますの長さ・幅員に関しては、以下の通りです。
| 対象車両 | 長さ | 幅員 |
|---|---|---|
| 軽自動車 | 3.6m | 2.0m |
| 小型乗用車 | 5.0m | 2.3m |
| 普通乗用車 | 6.0m | 2.5m |
土地上記の対象車両の数値を参考に、最低限の駐車場の寸法を確保するようにしましょう。また、乗り降りや荷物の積み下ろしなどでストレスを感じないためには、もう少し寸法にゆとりがあると安心です。
戸建ての狭い駐車場では、トラブルが発生するケースも少なくありません。なぜなら、日常的に利用するイメージが具体的にできていないためです。
具体的には、以下のようなトラブルの事例があります。
上記の事例の中で一番問題なのが、車種変更などで車が入らなくなるケースです。例えば、新築時には軽自動車に乗っていたため、軽自動車の駐車スペースしか作らなかった場合は、軽自動車よりも大きな車に買い替えると駐車場が使えなくなってしまいます。
このように、せっかく駐車場を作ったのにも関わらず、使えなくなってしまう場合もあるため、車の買い替えなどの今後の想定もしておくことが大切です。
また、自動車が入るギリギリで駐車場を設置してしまうと、思ったより使いにくいというケースも少なくありません。乗り降り・荷物を積み下ろし・バックドアの開閉など様々なシーンを想定しましょう。
上記のようなトラブルを防ぐためにも、住宅の設計のプロであるハウスメーカーや建築業者に相談するのがおすすめです。
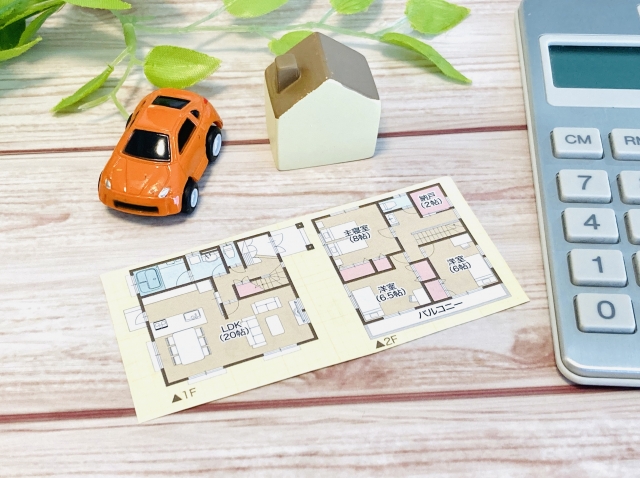
今回は、狭い土地に駐車場を作る際の問題点や工夫点について解説しました。狭い土地で駐車場を作る際は、駐車場や住宅の設計を工夫したり、別の手段を検討したりすることが大切です。
また、狭い土地に駐車場を作る際は、ただ車が入るスペースを確保するだけではいけません。人が乗り降りしやすいか、荷物の積み下ろしがしやすいか、駐車しにくくないかなど、実用シーンを具体的にイメージしましょう。
狭い土地を有効活用するには、ビルドインガレージにしたり、スキップフロア・ロフトなどを活用したり等、様々な活用方法があります。ぜひ本記事の工夫点等を参考に駐車場が作れるかどうか検討してみてください。
M-LINEでは、狭小住宅の建設等について豊富な知識と経験があり、狭小地の駐車場のご相談も承っております。お客様のご要望を伺った上で、土地の形状・周辺環境・住宅の設計等の様々な観点から最適なご提案をさせていただきます。
「他のハウスメーカーでは駐車場は難しいといわれた」「住宅の広さも確保したい」などのどんなお悩みでもぜひ一度ご相談ください。
2025/06/30
2025/06/30
2025/06/30