小林 眞一郎 ou2株式会社 常務取締役 二級FP技能士

2025/3/21(金)
二世帯住宅を検討しているけれど「なるべく費用を抑えたい」と考えている方も多いかと思います。賢く二世帯住宅を建てるには、補助金や助成金などの制度が利用できるか把握しておきましょう。
二世帯住宅で活用できる補助金は地域型住宅グリーン化事業、長期優良住宅化リフォーム推進事業などが挙げられます。ただし、これらの補助金を利用するには、利用条件に当てはまるかどうか、申請できるかどうかなどを確認することが大切です。
そこで、本記事では二世帯住宅で受けられる補助金の種類と、補助金を受ける際の注意点などを解説。また、二世帯住宅の補助金に関するよくある質問についても解説しているので、二世帯住宅の建築やリフォームなどを検討している方は参考にしてみてください。
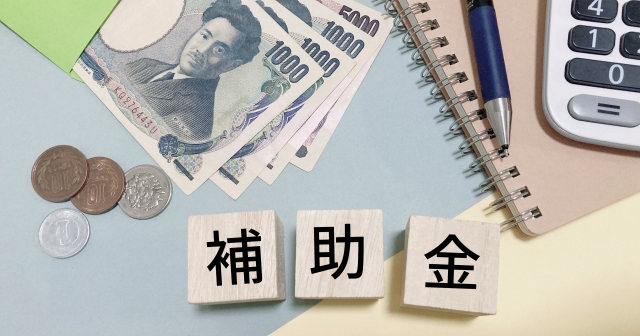
二世帯住宅で受けられる補助金は以下の4つです。
各補助金や助成金を利用する際は、制度の内容や条件について把握することが大切です。以下では補助金額や制度の内容、条件などについて解説するので参考にしてみてください。
地域型住宅グリーン化事業の補助金は、地域の中小工務店のグループ下で、低炭素住宅や長期優良住宅など省エネ性能に優れた木造住宅の新築を建てた場合に適用される制度です。
長期優良住宅・高度省エネ型の低酸素住宅または性能向上計画認定住宅を新築することで、70万~最大140万円の補助金が受け取れます。また、ゼロ・エネルギー住宅のみは改修(リフォーム)も補助金対象です。
| 対象 | 補助金額 | 条件 |
|---|---|---|
| 注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入 | 1戸につき70万円~140万円(※) ※地域材を半分以上使用した場合は20万円、三世代同居住宅の場合は30万円、バリアフリー対策に講じる場合は30万円を限度に 補助額の加算が適用された上限金額を表示しています。 |
・長期優良住宅や認定低炭素住宅、ゼロ・エネルギー住宅であること ・国土交通省で定められた中小工務店で建築すること ・主要構造部(建築基準法第2条第5号の定義による)が木造であること ・主要構造部に用いる木材は、グループが定める地域材を積極的に使用すること |
参考:令和5年度地域型住宅グリーン化事業 グループ募集の開始について|地域型住宅グリーン化事業(評価)
出典:地域型住宅グリーン化事業グループ募集要領【令和5年度】|地域型住宅グリーン化事業評価事務局
地域型住宅グリーン事業は、優良住宅や省エネ性能に優れた木造住宅の整備を目指すほか、三世帯同居の対応に対しての支援も目的としています。三世帯同居対応住宅とは、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち、いずれかの設備を2つ以上設置した住宅です。
三世帯同居住宅の加算で最大30万円の補助金を受け取れるため、二世帯住宅の設計の際に参考にするのも1つの方法でしょう。
参考:地域型住宅グリーン化事業グループ募集要領【令和5年度】|地域型住宅グリーン化事業評価事務局
すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担緩和のために作られた制度です。
こちらは1戸につき最大50万円の給付が受けられる制度ですが、2021年12月31日までに引き渡し入居が完了した住宅が対象となっています。
| 対象 | 補助金額 | 条件 |
|---|---|---|
| 注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入 | 1戸につき最大50万円 | ・住宅の所有者 ・住宅の居住者 ・収入が775万円以下である(目安) ・年齢が50才以上(住宅ローンを利用しない場合) ・住宅の床面積が50m2以上であること ・第三者機関の検査を受けた住宅であること ・引上げ後の消費税率が適用されていること |
国が行う補助金制度以外にも、市町村など一部の自治体で行っている補助金や助成金もあります。例えば、愛知県名古屋市が実施する「住宅等の低炭素化促進補助」が挙げられます。
この制度はZEHや太陽光発電設備、システム、家庭用燃料電池システムなどの導入の補助をする制度で、国のZEH補助と併用できるのが特徴。1件あたり10万円(ZEH+は20万円)補助が受けられるため、こうした補助金や助成金がないか自治体に確認してみましょう。
ただし、こうした制度は予算が決められているため、年度内に受け付けているかどうか下調べをして早めに申請を行うようにしましょう。
長期優良住宅化リフォーム推進事業とは、優良な住宅のストック形成・三世代同居対応改修工事・子育てしやすい環境の整備などを図るため、既存住宅の長寿命化や省エネ化などにかかる改修(リフォーム)にかかる費用を支援する制度です。
例えば、省エネルギー対策として断熱サッシへの交換、高効率給湯器などへの交換へのリフォーム費用などが補助されます。補助金額については、以下の通りです。
| 事業タイプ | 補助金限度額 |
|---|---|
| 評価基準型 | 100万円/戸 |
| 認定長期優良住宅型 | 200万円/戸 |
出典:令和4年度長期住宅化リフォーム推進事業に関する説明資料|国土交通省住宅局
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、以下の要件で補助金が受け取れます。
出典:令和4年度長期住宅化リフォーム推進事業に関する説明資料|国土交通省住宅局
ただし、リフォームの補助制度となるため、二世帯住宅の新築工事には適用できません。現在の家を二世帯住宅にリフォームしたい場合に利用できる制度なので注意しましょう。


下記の二世帯住宅の補助金制度はそれぞれ補助金を受け取るための条件と対象者が異なります。
それぞれの補助金制度には、異なる条件や対象者が設定されているため、事前にしっかりと確認することが重要です。
地域型住宅グリーン化事業は、長期優良住宅や省エネ性能の高い住宅を対象に、国土交通省が採択したグループが建設する住宅が条件となります。
すまい給付金は、住宅を取得する人の収入に応じて補助金が支給される制度です。「地域の住宅補助」は、各自治体ごとに独自の補助が用意されており、地域によって内容が異なります。
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、既存住宅の性能向上を目的としたリフォームを対象に補助が受けられる制度です。
これらの制度を活用することで、二世帯住宅の建築やリフォームにかかる費用を抑えることができます。
二世帯住宅の補助金を受けるためには、定められた条件を満たす必要があります。
補助の対象となるのは、長期にわたって住み続けられる長寿命型(長期優良住宅)や、省エネルギー性能が高い高度省エネ型(認定低炭素住宅・ゼロ・エネルギー住宅)、さらに一定の基準を満たした優良建築物型(認定低炭素建築物等)などの住宅です。
また、補助金の交付を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たすことで、補助金の対象となります。補助金の活用を検討する際は、詳細を自治体や国の制度を公式サイトや窓口で確認しながら進めることが大切です。
ここでは、補助金の対象外となってしまったケースを紹介いたします。
Aさんは築30年の実家を二世帯住宅へとリフォームし、快適な住環境を整える計画を立てていました。リフォームには相応の費用がかかるため、補助金制度を活用しようと調べたところ、「地域型住宅グリーン化事業」が高性能な住宅改修にも適用されることを知り、補助金を受ける前提で計画を進めていました。
しかし、2022年度から制度の対象が新築のみとなり、住宅改修は補助の対象外になってしまいました。Aさんは突然の変更に戸惑いましたが、別の補助制度を探し、最終的には「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の活用を検討。断熱性能の向上や耐震補強を行うことで補助金を受けられることがわかり、リフォーム計画を調整しました。
結果的に当初の計画より自己負担額は増えたものの、補助金を受けながら二世帯住宅として快適に暮らせる家づくりができたAさん。補助金制度は年度ごとに変わるため、事前に最新の情報を確認することが重要だと実感したそうです。

二世帯住宅の補助金を利用したいと思っている方は、以下の4つの点に注意しましょう。
国や自治体の補助金を受けるには、細かい条件が定められていたり、予算が決められていたりします。補助金を確実に利用するためには、事前準備をしっかり行いましょう。
二世帯住宅で補助金を利用する際は、締め切りの期限を確認しましょう。締め切りの期限を確認する理由としては、二世帯住宅で利用できる補助金は予算が決まっている場合が多いからです。
また、申込の期限を確認しても、予算上限に達した時点で締め切りという条件をつけている補助金も少なくありません。
そのため、申込締め切りの期日だけを見てスケジュールを立てるのではなく、早い段階で補助金を活用するのかスケジュールを組む必要があるでしょう。
二世帯住宅を建てる際に、補助金の対象条件の確認が必要です。なぜなら各補助金や助成金の制度では、対象条件に満たしていなければ補助金や助成金を利用できないからです。
例えば、地域型住宅グリーン化事業では、「長期優良住宅や認定低炭素住宅、ゼロ・エネルギー住宅であること」「国土交通省で定められた中小工務店で建築すること」などの複数の条件があります。
条件を満たすか否かについては個人で確認すると不備がある可能性もあるため、ハウスメーカーや工務店、自治体など補助金や助成金について詳しいプロに確認してみましょう。ハウスメーカーや工務店では、条件を満たすように二世帯住宅を設計したり選んだりすることが可能です。
補助金や助成金の申込期日などもあるため、利用したい場合は早い段階で相談するのがおすすめです。
二世帯住宅で補助金や助成金を利用する際は、手続きのミスや書類の不備がないかチェックしましょう。理由としては、不備があると補助金の支給が遅くなったり受け取れなくなったりする可能性があるからです。
申請手続きは担当したハウスメーカーや工務店などが行ってくれる場合が多いですが、ご自身で用意してもらうものもあるため、漏れなくそろえるようにしましょう。心配なことがあれば、助成金や補助金の窓口に問い合わせ、内容をチェックしてもらってください。
二世帯住宅で補助金や助成金で注意したいのが、補助金の支給は事後になる点です。補助金や助成金は二世帯住宅が完成した後に支給されるため、補助金を差し引いた金額で資金計画を建てないようにしましょう。
また、補助金の支給額についても要チェック。補助金のなかには、補助金の支給の際に申請費用が引かれる補助金があります。資金の用意や補助金がどのように支給されるのか、事前に確認しておきましょう。
さらに、補助金には申請期間や予算上限が設けられている場合があるため、早めの申請が重要です。

ここからは、二世帯住宅に関する税源措置についてや活用方法、減税制度などをも紹介していきます。
不動産取得税の軽減措置は、住宅を購入する際に経済的な負担を軽減するための制度です。通常、不動産取得税は取得価格の3%が課税されますが、特定の条件を満たすと軽減措置が適用されます。
例えば、新築住宅の場合、一定の面積要件を満たすことで、課税標準額から1,200万円が控除されます。中古住宅でも築年数や耐震基準を満たすことで、同様の控除が受けられる場合も。このような軽減措置は、住宅を取得しやすくするための優遇策として、多くの購入者に利用されています。最新の条件や手続きについては、自治体の窓口や専門家に相談することがおすすめです。
二世帯住宅の固定資産税を軽減するための制度には、二世帯住宅や新築住宅に特化したものがあります。
例えば、玄関や室内が完全に分離していると、2つの住宅として認定されることがあります。この場合、「新築住宅にかかる固定資産税減額措置」が適用される可能性があり、1世帯につき120㎡までの固定資産税が最長3年間、税額の1/2が減額。240㎡までが減額対象なので、注意してください。
しかし、この制度は、2026年3月31日までとなっています。また、家屋が共有名義であることなど、特定の条件を満たす必要があるので、事前に自治体で詳細を確認することが重要です。
さらに、新築した二世帯住宅が認定長期優良住宅である場合、減額期間が5年に延長される特典もあります。このように、制度をうまく活用することで、二世帯住宅の固定資産税の負担を軽減することが可能です。
二世帯住宅などの一般住宅の場合の登録免許税の減税を受けるための条件は以下の5つです。
国税庁の「土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」も併せて確認してください。
参考記事:土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ|国税庁
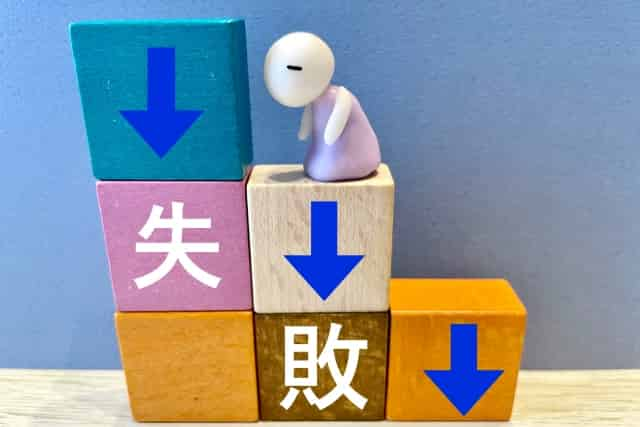
ここからは、二世帯住宅のよくある以下の3つの失敗事例と回避策について解説していきます。
二世帯住宅では、来客時のプライバシーが問題になることがあります。例えば、完全共有型の二世帯住宅では、親世帯の来客がリビングを利用するため、子世帯が気を遣い自由にくつろげないというケースが。
また、玄関が共有の場合、来客の出入りが丸見えになり、プライバシーを確保しにくいと感じることもあるでしょう。
このような失敗を回避するには、玄関を分ける、リビングの動線を工夫するなどの対策が有効です。例えば、親世帯と子世帯それぞれにリビングを設けることで、互いの生活空間を確保できます。
また、来客用の導線を工夫し、直接親世帯の空間へ案内できるようにすると、子世帯が気兼ねすることなく過ごせます。設計段階でプライバシー確保を意識することが、快適な二世帯住宅づくりの鍵です。
二世帯住宅では、生活音のトラブルがよく発生します。例えば、上下分離型の場合、子世帯の足音や子どもの走り回る音が親世帯に響き、ストレスの原因になることも。また、キッチンや水回りの配置によっては、朝晩の生活リズムの違いから、物音が気になるケースもあります。特に早朝や深夜のテレビや家電の音が問題になり、気を遣いながら生活しなければならない状況に陥ってしまうのです。
このようなトラブルを回避するには、防音対策をしっかり行うことが重要です。例えば、床材や壁材に遮音性の高いものを使用したり、天井に防音シートを施工することで、音の伝わりを軽減できます。また、間取りの工夫も効果的で、親世帯の寝室の上に子世帯のリビングを配置しないなど、音が響きにくい設計を考えることが大切です。
二世帯住宅では、住宅のメンテナンス費や生活費の負担についてトラブルが発生しやすいです。例えば、共用部分の修繕費や光熱費の分担が曖昧なまま生活を始めた結果、どちらの世帯がどれだけ負担すべきかで揉めるケースがあります。また、築年数が経つにつれ修繕費がかさみ、想定以上の負担となってしまうこともあります。親世帯が退職し収入が減少した際に、子世帯だけが負担を抱える事態になることも少なくありません。
こうしたトラブルを回避するには、事前にメンテナンス費や生活費の分担を明確に決めておくことが重要です。例えば、光熱費は別々に計算できるようメーターを分ける、修繕費は毎月一定額を積み立てるなどのルールを作るとよいでしょう。事前に家計管理の方法を話し合い、将来の負担増も見越した資金計画を立てることが、安心して暮らせる二世帯住宅のポイントです。

ここからは、二世帯住宅に関するよくある質問について解説します。
二世帯住宅のリフォームで補助金が受けられるか、どこのハウスメーカーや工務店に依頼すればよいのかなどを紹介しているので、参考にしてみてください。
二世帯住宅のリフォームでは「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の補助金が利用できます。
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、優良な住宅のストック形成、三世代同居対応改修工事、子育てしやすい環境への整備などを図るため、既存住宅の寿命化や省エネ化などにかかるリフォームに費用を支援する補助金制度です。
二世帯住宅のリフォームの場合は、キッチンや玄関、浴槽などの増設などによって補助金が受けられます。その他の助成が受けられるリフォーム工事内容は、以下のような例が挙げられます。
| 性能向上リフォーム | ・劣化対策 ・省エネルギー対策 ・耐震性 ・維持管理・更新の容易性など |
| 維持保全計画の作成 | 維持管理更新容易性の向上 |
| 三世代同居対応改修 | キッチン・玄関・浴槽などの増設 |
| 子育て世帯向け改修 | キッズスペースの設備、防犯カメラの設置 |
| 防災性・レジリエンス性の向上改修 | 自然災害に対応する改修への支援 |
出典:令和4年度長期優良住宅化リフォーム推進事業に関する説明資料|国土交通省住宅局
新しく二世帯住宅を建てるより、今住んでいる住宅をリフォームすれば費用を抑えられ、助成金が受けられるメリットがあります。さまざまな方法を考慮し、二世帯住宅の建築について考えてみましょう。
二世帯住宅の新築やリフォームなどの費用の助成金が受けられるのは、国や地方自治体の公募によって採択されたハウスメーカーや工務店のみと定められている場合があるので注意しましょう。
例を挙げると、長期優良住宅(木造)補助金の場合は、国土交通省で定められた中小工務店のみとなっています。
地域型住宅グリーン化事業の補助金を利用したい場合は、以下のサイトで地域の工務店を調べてみましょう。
参考サイト:~長期優良住宅補助実施中小工務店の検索サイト~|一般社団法人 木を活かす建築推進協議会
大手ハウスメーカーで二世帯住宅を建てる場合は、長期優良住宅(木造)補助金が受けられないため注意が必要です。上記で検索する以外にも、各工務店に補助金が利用できるかどうか確認すると安心です。
二世帯住宅は、補助金・助成金以外にも、さまざまな税金の優遇措置があります。二世帯住宅の税金の優遇措置が受けられるのは、以下の4つが挙げられます。
まず、不動産所得税については、課税標準額×税率で算出され、課税標準額を減額する措置があり、二世帯分の軽減措置が受けられる可能性があるのがメリットです。なぜなら不動産所得税の特例控除は一世帯あたり1,200万円と定められているため、二世帯住宅の最大2,400万円の控除が受けられる可能性があるからです。
不動産所得税は、下記のように50㎡以上で240㎡以下の床面積で居住の要件を満たす新築住宅の場合、一世帯あたり1,200万(認定長期優良住宅の場合は1,300万)の軽減措置が受けられます。
| 対象 | 下限 | 上限 |
| 新築住宅の床面積要件 | 50㎡以上 | 240㎡以下 |
参考:不動産所得税|東京主税局
次に住宅ローンの減税について説明します。住宅ローンの減税も、二世帯住宅は二世帯分控除が受けられる可能性があります。なお、各世帯で住宅ローンを組むことが前提です。
住宅ローン減税は、年末時点での住宅ローン残高のうち0.7%が所得税や住民税から13年間にわたって控除される制度です。二世帯とも適用される条件は、共有登記等されていること、一世帯あたりの延べ床面積が50㎡以上、居住空間が2分の1以上などが挙げられます。
参考:No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
また、二世帯住宅の固定資産税は、土地や建物の軽減措置を二世帯分受けられる可能性もあるのです。固定資産税は、課税標準×税率で算出され、小規模住宅用地の特例が適用されれば、一世帯あたり200㎡までの家屋が建つ土地は固定資産税の課税標準額が6分の1に、都市計画税が3分の1に軽減されます。
そのため、二世帯住宅の場合、2戸分で最大400㎡までの軽減措置が受けられる可能性があります。
建物の固定資産税は、新築の二世帯住宅を建てた場合、延床面積が最大240㎡までが3年間2分の1(長期優良住宅等は5年間)に課税標準を軽減できる可能性があるのがメリット。1戸分の場合は120㎡までしか受けることができないため、大きな減税効果となるでしょう。
さらに二世帯住宅は、「共有登記」または「単独登記」の場合、相続税の軽減措置が受けられます。理由としては、相続税の計算の概要として、(相続財産の評価額-基礎控除)×税率で求められ、上記の場合は一定の要件を満たせば、「小規模宅地等の適用」がされる可能性があるため、相続する土地の面積330㎡までの評価額を80%減額が可能だからです。
ただし、小規模宅地等の適用を受けるためには、完全分離型などで親世帯と子世帯が区分登記をしないことがポイント。なぜなら、区分登記にしてしまうと別々の住宅に住んでいるとみなされてしまい、小規模宅地等の適用がされないからです。
こうした税の優遇措置の要件は個人の判断が難しいため、ハウスメーカーや工務店、地方自治体、税の専門家等などに相談すると安心でしょう。

二世帯住宅を新築する際や、リフォームする際には利用できる補助金が多数あります。少子化対策の一環として、家事や育児がしやすい三世代同居に伴う建築費用やリフォーム費用の補助などが増えていくことも予想されます。
ただし、補助金を利用する際は制度の条件や申請期限、予算などを十分に確認し、利用できるかどうかハウスメーカーや工務店と相談しておきましょう。
M-LINEでは、二世帯住宅の設計、建築、補助金などの相談も承っています。「二世帯住宅の建築費用を安くしたい」「ストレスを感じにくい家づくりにしたい」などどのようなご相談でも一度ご相談ください。
二世帯住宅の建築・補助金・税金に関する豊富な経験と実績を持つ専門スタッフがお客さまのご要望を伺った上で、最適な提案をさせていただきます。