小林 眞一郎 ou2株式会社 常務取締役 二級FP技能士

「しっかり儲けたい」「老後資金に備えたい」「税金対策をしたい」などの理由で賃貸アパート経営を始めたいと考えている方もいるでしょう。
しかし、知識不足で賃貸経営を始めてしまうと、ハウスメーカーや建築会社の話が理解できなかったり、安定した収入を得られなかったりといった事態に陥ってしまうことも…。賃貸アパート経営を始める際は、賃貸経営の知識を身につけ、綿密な収支計画を立てることが大切です。
本記事では賃貸アパート経営の始め方や特徴、基本的な流れについて徹底解説します。賃貸経営に興味がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

賃貸経営の始め方には、主に以下の4つのパターンがあります。
それぞれの特徴や、始める際のポイントについて詳しく紹介します。
1つ目の始め方は、すでに所有している土地を活用してアパートを建築する方法です。土地購入費が不要なため、初期投資を抑えやすいのが大きな利点です。この方法には、以下のようなメリットがあります。
一方で、以下のような注意点もあります。
すでに所有している土地を活用したアパート建築は、4つの方法の中でも最も初期費用を抑えやすく、条件が整えば安定した収入を得やすい手堅い選択肢です。成功のためには、どのような入居者の需要が見込まれるかを的確に判断することが大切です。
2つ目の始め方は、新たに土地を購入してアパートを建築する方法です。土地の選定から建物の設計までを一貫して行えるため、自分の方針に沿った賃貸物件を構築できることが特徴です。この方法には、以下のようなメリットがあります。
一方で、以下のような注意点もあります。
新たに土地を購入してアパートを建築する方法は、初期投資や準備が多く必要ですが、その分自由度が高く、長期的な資産形成につながる有力な選択肢といえます。
3つ目の始め方は、中古アパートを購入して賃貸経営を始める方法です。新築に比べて初期費用を抑えやすく、高利回りが狙えることから初心者にも人気があります。特に、少ない資金で早期の収益化を目指す方にとっては有力な選択肢となるでしょう。この方法のメリットは、以下の通りです。
一方で、以下のような注意点もあります。
中古アパート経営はリスクを理解し適切に対策を講じることで、安定した収益を目指せる有力な選択肢です。
4つ目は、新築アパートを購入する方法です。新築物件は築浅で設備が新しく、入居希望者からの注目度も高いため、満室経営を実現しやすい傾向にあります。デザインや仕様にこだわることで、周辺の中古物件との差別化も可能です。
この方法には、以下のようなメリットがあります。
一方で、以下のような注意点もあります。
新築アパート経営は高額な投資になりますが、戦略的に進めることで安定した賃貸収入を得られる可能性があります。物件選びと資金管理の精度が、成功のポイントとなるでしょう。

賃貸アパート経営のメリットは、以下の3つです。
賃貸アパート経営を始めるかどうか迷っている方は、ぜひメリットを押さえておきましょう。
賃貸アパート経営は、長期的に家賃収入が得られるのがメリットです。なぜなら、アパートの入居者がいれば、安定的に家賃収入が見込めるからです。
また、株式投資やFXなどと比べて急激に価値が暴落したり、空室が発生したとしても収益が急にゼロになったりというリスクも少ないでしょう。
令和5年度の国税庁の申告所得税標本調査結果を見ても、賃貸経営の平均の合計所得額は約547万円と安定的な収入を得られていることが分かります。賃貸経営によって得られる収入を、生活資金の補填や老後資金の備えとして活用することが可能です。
賃貸アパート経営には、相続税や固定資産税などの節税効果があるのもメリットです。相続税については現金をそのまま相続するより、土地や建物などの不動産で相続した方が相続税評価額が低くなる傾向があります。
相続税評価額が低くなる理由は、アパートが建っている土地は「貸付建付地」として扱われ、一定の条件を満たすことで、建物や土地に相続税の軽減措置が適用されるためです。なお、評価額の軽減は、借地権割合や賃貸割合などによって異なります。
詳しくは以下の表を参考にしてみてください。
| 対象 | 計算方法 |
|---|---|
| 建物の相続税評価額 | 固定資産税評価額×( 1-借家権割合(0.3)×賃貸割合) |
| 土地の相続税評価額 | 相続税評価額×(1-借地権割合(※)×借家権割合(0.3)×賃貸割合) |
※30~90%で各地域によって異なる、路線価図に記載
また、アパート経営の不動産所得は、高額な減価償却費を毎年経費に計上できるため、節税効果が高いのもメリットです。不動産収入以外に給与所得がある場合は、損益通算ができます。
空室などの理由でアパート経営が赤字になった場合でも、給与所得と損益通算し、所得税の還付や翌年の住民税を低減することが可能です。
賃貸経営の節税効果については、以下の記事で詳しく解説しています。
アパート経営は、成功率が高いといわれています。成功率が高いといわれる理由としては、アパート経営の利回りは全国で平均8%と高く、他の土地活用と比べても収益性に優れている点が挙げられます。
実際、他社のWebサイトによるアンケート調査では、アパート経営に「満足している」と回答したオーナーが約7割にのぼる結果もみられます。とはいえ、アパート経営の成功の基準は人それぞれ異なるため、一概に7割成功するとは言い切れない点には注意しましょう。
また、アパート経営が成功するかどうかは、立地や需要レベルによっても大きく左右されます。アパート経営を成功させるためには、綿密な立地調査や収支計画を立てる必要があるでしょう。


賃貸アパート経営には魅力的なメリットがある一方、以下のようなデメリットも存在します。
順に詳しく解説します。
賃貸アパート経営を始める際のデメリットは、多額の初期費用が必要になる点です。例えばアパートを新たに建てる場合は、建築費用がかかります。建築費用は構造や規模によって異なりますが、木造アパートの場合、坪単価はおよそ70万〜100万円が相場です。
土地を新たに購入する場合は、土地の取得費用が加わるため、初期投資はさらに膨らみます。
そのほかにも、電気や水道の引き込み工事、地盤改良工事などの付帯工事費がかかります。さらに、不動産取得税や登記費用、契約書に貼る印紙税、火災保険や地震保険の保険料なども忘れてはいけません。また、アパートローンを組む場合は、保証料や事務手数料も必要になります。
初期費用の高さは賃貸アパート経営における大きなハードルのひとつといえます。
以下の記事では、アパート経営に必要な初期費用について詳しく解説しています。併せて参考にしてみてください。
空室リスクについてもしっかりと把握しておくことが大切です。空室が続けば家賃収入が得られず、経営がうまくいかなくなるおそれがあります。特に金融機関からの借入でアパートを取得・建築している場合、収益が途絶えることで返済に支障をきたすリスクも否定できません。
さらに、空室の長期化によって以下のような悪影響が生じる可能性もあります。
空室リスクに備えるためには、立地の選定や家賃設定の見直し、魅力的な設備投資、信頼できる管理会社の活用など、早期からの戦略的な空室対策が欠かせません。安定した賃貸経営を続けるためにも、最初の段階から空室リスクに対する備えをしっかりと意識しておくことが重要です。
以下の記事ではアパート経営で空室が出てしまう具体的な原因や対策方法について解説しています。気になる方はぜひ参考にしてみてください。
賃貸アパート経営は安定した収益が期待できる一方で、トラブルに発展するリスクも存在します。以下は、賃貸アパートにおける代表的なトラブルをまとめたものです。
これらのトラブルを防ぐためには、入居者にルールを丁寧に説明し、問題が発生した際には迅速に対応することが重要です。安定した賃貸経営を続けるためには、収益面だけでなくリスク管理にも十分注意を払う必要があります。

賃貸アパート経営を始める際に必要な事前準備は、以下の通りです。
賃貸アパート経営では、知識を身につけたり、目的や目標を決定したりするなど事前準備が大切です。賃貸アパート経営についてよく分からない方は、流れに沿って事前準備を行ってみてください。
賃貸アパート経営を始める際は、賃貸経営の知識を身につけることが大切です。理由としては、建築基準法や宅建業法などの法律、運用するための会計や税金など不動産に関してのさまざまな知識を持っておくことで、賃貸アパート経営の判断に役立てることができるからです。
例えば、アパートを購入する際、契約や手続きのときに登記や法律について理解できなければ、ハウスメーカーや建築業者の話を理解するのが難しいでしょう。また、不動産に関する情報収集力や判断力があれば、いい物件をすぐに購入できます。
さらに、副業として賃貸アパート経営を考えているなら、損益通算の仕組みや確定申告のやり方なども理解しておく必要があるでしょう。アパートへの投資は、高額な借入金を行うため、失敗しないためにもさまざまな知識を身につけることが大切です。
賃貸経営の知識をある程度習得したら、アパート経営の目的と目標を設定しましょう。目的と目標を適切に設定することで、自己資金はどのくらい必要か、どのような物件を建てればよいかなどの判断材料になります。
例えば、老後の資金形成を目的とした場合、どのくらいの家賃収入があれば実現できるのかを判断しやすくなるでしょう。目的と目標を具体的にすることで、定期的に目標の数値と合っているのか、経営判断にも役立ちます。
賃貸経営には「節税対策をしたい」や「不動産所得を得たい」などさまざまな目的があるため、明確にして自己投資がいくら必要で、いくら借入をするのかなどを判断しましょう。
賃貸経営を始める際は、ターゲットを明確に設定することが大切です。なぜなら、アパートの立地の賃貸需要を把握してターゲットの需要に合った物件を建てることで、空室や家賃下落のリスクを抑え、収入を安定させられるからです。
例えば、小学校が近い立地なら、2LDKや3LDKといったファミリー世帯の間取りのアパート経営が適しています。収納を多くしたり、お風呂やキッチンの設備をよくしたりするなど、ターゲット層のニーズに合った間取りや設備を準備することで、空室のリスクを軽減できるでしょう。
賃貸経営を始める際は、綿密な収支計画を立てることも大切です。理由としては、具体的な収支計画を立てることで、アパート経営のより現実的な数値を把握しやすくなるためです。
具体的には、ターゲット層のニーズに合ったアパートの建築費用(初期費用)・税金・管理料・仲介料など、あらゆる費用の目安を算出しましょう。また、アパート経営には一定の空室・家賃下落のリスクがあり、10年〜20年後にはリフォーム代や修繕費が必要になります。
さまざまな費用やリスクも想定し、収支計画を立てることで、どのくらいの期間で初期費用を回収して黒字化できるかの判断にも役立ちます。ただし、収支計画を個人で行うのは難しい部分も多いため、不動産業者や建築会社などのプロに現実的なシミュレーションをしてもらうのがおすすめです。
相続税対策などでアパート経営を行う際は、相続する可能性のある家族と話し合いをしておくのも重要なポイントです。理由としては、アパート経営は約30年以上と長期に渡るため、オーナーに万が一のことがあった際に家族が管理をしなければならないためです。
相続税の負担が軽減するからといっても「不動産の管理はしたくない」「リスクを背負いたくない」というご家族もいるでしょう。相続する可能性がある方には、どのような経営方針なのか、収支計画はどうなっているのかなど、始める前にきちんと説明をしておきましょう。

賃貸アパート経営の始め方は、以下の通りです。
アパート経営では、建築会社の選び方、建築会社とのやり取りなどの流れも把握しておくのがおすすめ。建築期間や入居者募集のイメージなどをつけておき、実際に賃貸アパート経営を行う際の参考にしてみてください。
建築会社を選ぶ際は、複数の会社を比較するのがポイントです。理由としては、ハウスメーカーや建築会社によって、アパートの工法・構造・建築費用が違うからです。
また、所有する土地のエリアに詳しいかどうか、実績があるかどうかも建築会社の重要な選定ポイントとなります。土地に適した設計や収支計画が立てられれば、失敗するリスクも低くなるでしょう。
1つ1つの建築会社に問い合わせるのが難しい場合は、一括請求プランなどを活用し、効率的に建築会社を比較してみましょう。
建築会社とのやり取りでは、なるべく現実的なプランや数値を提案してもらうのがポイントです。賃貸アパート経営の目的、目標を具体的に伝え、いくら収益をあげたいのかを明確に伝えましょう。
例えば「年間〇〇万円の収益をあげたい」と明確にすることで、その目的に合った立地選びやアパートの構造・間取り、家賃設定といった具体的なプランを立てやすくなります。
また、初期費用の安さだけで判断せず、長期的な視点で収支計画を立てるのも成功するコツです。
理由としては、建築費などの初期費用を安くするとグレードが低い物件となり、家賃設定が安くなったり、リフォームや修繕費が嵩んだりする物件となる可能性があるからです。初期費用だけでなく、数年先の支出や収入も見越して、入居率が維持できる物件を建てましょう。
一般的な2階建ての木造・軽量鉄骨造のアパートの建築期間は、3ヶ月〜6ヶ月程度が目安です。鉄骨造・RC造の場合は、アパートの回数+2ヶ月〜3ヶ月程度を目安としましょう。
規格化されたハウスメーカーや建築会社を選ぶと、さらに短い建築期間となる可能性もあります。竣工後は、入居者募集・管理業務などさまざまな業務を行う必要があるため、下調べしたり、建築会社から提案を受けたりして準備しておきましょう。
賃貸アパートの完成の目途がついたら、入居者募集内容を決めましょう。建築会社とのやり取りで計画した賃料に加え、敷金や礼金、管理費や保証金などの額を決める必要があります。
次に、入居者の募集要項を決めましょう。入居者の募集要項とは、大家さんが入居者募集の注意事項や契約に関して記載した書類です。例えば、以下のようなことを募集要項に記載します。
賃貸アパート経営の入居後は、日常的なメンテナンスを行う必要があります。理由としては、アパート経営では、ゴミ置き場のチェック、エントランスや駐車場など共用部分の清掃、消火器や火災報知器の点検など、さまざまなメンテナンスが必要になるからです。
これらのメンテナンスは、オーナー自身で行う場合と管理業者に委託する方法があります。オーナーが自主管理する場合は、管理費用を抑えられますが、毎回アパートに出向いて管理業務を行う手間がかかります。
一方で管理業者に委託する場合は、清掃や点検などの管理業務をすべて任せられます。さらに、管理業者はトラブルやクレーム対応にも適切に対応してくれるでしょう。
管理業者にはさまざまな会社があるため、費用やサービスなどを比較して検討するようにしましょう。
賃貸アパート経営を始める前には、資金計画の確認と再検討を行いましょう。計画の段階で現実的な計画を立てたとしても、実際に準備を進めていくうちにズレが生じる可能性があるためです。
資金計画にズレが生じた場合は、その分の資金を確保したり、費用の見直しを行ったりする必要があります。長期的な運用を成功させるためには、賃貸アパート経営を始めた後も、キャッシュフローは常に正確に把握しておくことが大切です。
パートナーとなるハウスメーカーや建築会社と資金計画の確認と再検討を行い、賃貸アパートの成功率を高めましょう。

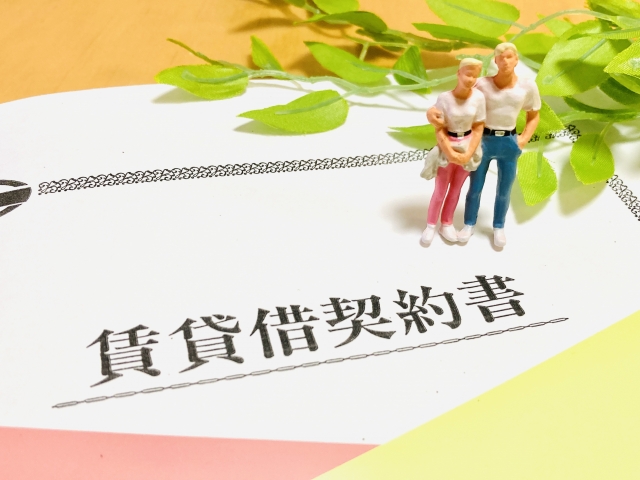
入居者募集から入居後の賃貸アパート経営の始め方は、以下の通りです。
賃貸アパート経営は、建てたら終わりではなく、実際に入居者を募集したり入居後の管理やメンテナンスを行う必要があります。ここでは、実際の流れや内容について紹介するので、チェックしてみてください。
賃貸アパートが完成したら、入居者の決定と賃貸契約の締結を行います。入居者の募集は、地域の需要を把握した不動産仲介会社に依頼しましょう。
入居希望者の申込を受けたら、いよいよ入居者の決定です。入居者の申込書には、一般的に入居希望者・連帯保証人の氏名・住所・勤務先・年収・電話番号などを記載してもらいます。
この申込書の情報を基に、入居者の審査が行われ、審査が無事完了したら賃貸借契約の締結です。貸主と借主双方が賃貸借契約書の内容を確認し、署名・捺印を行う流れとなります。
これらの契約に関わる業務は、基本的に不動産仲介業者が行ってくれますが、双方のトラブルとならないためにも契約の際にはしっかりと確認を行いましょう。
賃貸アパート経営の入居者が決まれば、入居者・賃貸管理が必要になります。例えば、賃料の管理や苦情への対応、契約違反などの対応が挙げられます。
また、契約更新の意思確認や、更新の契約の準備、退去の立ち合いや手続きなども行わなければなりません。賃料滞納や苦情の対応は入居者とのトラブルになるケースも多いため、費用に余裕があれば、管理会社に任せることをおすすめします。
入居者が決まった後は、日常的なメンテナンスを行いましょう。アパート経営ではゴミ置き場のチェック、エントランスや駐車場など共用部分の清掃、消火器や火災報知器の点検など、さまざまなメンテナンスが必要です。
自分がどの程度アパートのメンテナンスに関われるかを考慮して、管理業者を利用するかどうかを検討しましょう。

賃貸経営を成功させるためのコツは、以下の3つです。
順に解説していきます。
賃貸経営では、立地が収益を左右する最大のポイントです。駅からの距離や周辺の買い物施設、病院、学校などの利便性は、入居者の意思決定に大きく影響します。特に駅から徒歩15分以内の物件は人気が高く、空室リスクが低くなります。
立地は後から変えられないため、購入前に慎重に見極める必要があります。周辺の人口動態や開発計画など、将来の成長性もチェックしましょう。また、物件のタイプと地域の特性が合っていれば、より多くの入居希望者を惹きつけることができます。
すでに土地を持っている場合でも、その立地に合ったターゲット層を想定することが大切です。駅や商業施設が近ければ単身者向け、子育て支援が充実した地域ならファミリー層向けの設計が有効です。
立地の選び方次第で、経営の安定度は大きく変わります。地域の特性を正しく把握し、戦略的に活用することが成功への第一歩です。
賃貸経営を成功させるためには、リスク管理が欠かせません。安定した運営を実現するには、さまざまなリスクを正しく理解し、適切に対処することが求められます。以下は主なリスクとその対策をまとめた表です。
| リスクの種類 | 内容 | 対策例 |
|---|---|---|
| 空室リスク | 空室が続き家賃収入が得られなくなる。 | 地域の需要を見極め、適切な家賃設定を行う。 |
| 家賃滞納リスク | 入居者が家賃を支払わないことによって収益が減少する。 | 信頼できる入居者を選定する。保証会社の活用も有効。 |
| 物件の老朽化リスク | 建物の老朽化によって住居環境が悪化したり修繕費が増加したりする。 | 定期的な点検とメンテナンスを実施。 |
| 自然災害リスク | 地震や火災などで建物が損傷する。 | 耐震性の高い建物設計。適切な保険へ加入する。 |
こうしたリスク管理を徹底すれば、安心して長く賃貸経営を続けるための土台を築けるでしょう。
賃貸経営を安定させるには、信頼できる管理会社の存在が大きな支えになります。業務を任せられるパートナーがいれば、手間を減らしながら効率的に運用でき、リスクも軽減されるでしょう。
管理会社は、入居者募集・賃料管理・設備の維持・トラブル対応など幅広い業務を担います。これらを専門家に任せることで、オーナーは本業や私生活に集中しやすくなります。また、問題が起きた際にも、経験豊富なスタッフが迅速に対応してくれるのは安心材料です。
ただし、管理会社ならどこでもいいわけではありません。実績や地域への理解、対応の丁寧さなどを比較し、自分に合った会社を見極めることが大切です。報告や相談がしやすい会社であれば、信頼関係も築きやすくなります。
よい管理会社との出会いは、賃貸経営の成功を左右する重要なポイントです。長期的なパートナーとして選ぶ意識を持ち、慎重に判断しましょう。

最後に、賃貸経営の始め方に関するよくある質問3つにお答えします。
疑問点を解消し、安心して第一歩を踏み出せるようにしましょう。
アパート経営で元を取るまでの期間は、立地や物件の規模、融資条件、空室率などによって大きく異なります。一般的な目安としては、5〜10年程度が多いとされています。
ここでいう「元を取る」とは、物件の購入費や諸経費、リフォーム代など初期投資額を家賃収入で回収することを指します。ただし、利回りや経営状況によって実際の回収期間は変わります。
例えば、表面利回りが8%なら単純計算で約12.5年、10%なら約10年で回収可能とされますが、空室や修繕費、ローン返済の影響で実際にはさらに時間がかかることもあります。
アパート経営は短期的な利益ではなく、長期的に安定した収入を得るための事業です。物件の特性や地域性をしっかり分析し、現実的なシミュレーションに基づいた回収計画を立てることが成功のカギとなります。
令和5年度の国税庁「申告所得税標本調査」の結果によると、賃貸オーナー(不動産所得がある人)の平均所得額は約547万円となっています。
ただし所得額は物件の規模や立地、所有戸数、ローンの有無、管理の方法などによって大きく異なります。戸建て1棟だけを所有する兼業オーナーと、複数のアパートを保有する専業オーナーとでは、得られる収入に大きな差があります。
また、家賃収入が高くても、ローン返済・修繕費・管理費・固定資産税などの必要経費を差し引いたあとの実際の利益は平均よりも少なくなることがあります。
平均年収を参考にしつつ、自分の物件状況に応じた収支計画を立てることが重要です。
アパート経営とマンション経営のどちらがより儲かるかは、物件の立地や規模、資金力、経営方針などによって異なります。
一般的に、アパートは少ない資金で始めやすく、高い利回りを狙いやすいのが特徴です。ただし、収入の絶対額はマンションに劣る場合があります。一方で、マンションは安定した収入と資産価値の高さが魅力ですが、初期投資が大きくなりやすい傾向があります。
どちらが儲かるかは一概にいえないため、自身の資金計画やリスク許容度、投資目的に応じて適切な選択をすることが大切です。
以下の記事ではマンション経営のメリットや注意点などについて解説しています。アパート経営とマンション経営のどちらを選ぶべきか迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

賃貸アパート経営は、長期的に家賃収入が得られたり、節税効果があったりとメリットも多いです。本記事で紹介した始め方を参考に、事前準備や勉強を行えば成功率も高まることが期待できます。
賃貸アパート経営は、大きく分けて事前準備、建築会社の選定や建築・竣工まで、入居後の管理の3つに分けられます。それぞれの内容や流れを理解し、賃貸アパート経営を適切に行えるように準備しましょう。
M-LINEでは多数の賃貸アパート経営の提案実績があるため、賃貸アパート経営の始め方についてのご相談も承っています。
「賃貸アパート経営に興味がある」「資金面に不安がある」「収支計画の相談に乗ってほしい」など、どのようなお悩みも一度ご相談ください。