小林 眞一郎 ou2株式会社 常務取締役 二級FP技能士

10坪・15坪・20坪といった狭小地でもアパート経営ができるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
狭小アパートは、都心部や駅が近いなど利便性が高い地域は需要があります。狭小アパートは面積が小さい分、土地代や固定資産税などのコストが低く、入居率が高ければ高利回りも狙えます。
ただし、狭小地は建築工事の際に不便な点が多く、建築費が高額になったり施行期間が長くなったりするデメリットもあるため注意が必要です。
この記事では、10坪・15坪・20坪程度の狭小地のアパート建築・経営についてや、狭小アパートの特徴、狭小地でアパート経営するメリット・デメリットについて詳しく解説します。
「狭小地を所有している」「狭小地の土地活用を検討している」という方は、ぜひ一度参考にしてみてください。

結論からいうと、狭小地でもアパートの建築・経営は可能です。狭小地とは、10坪・15坪・20坪などの狭い土地のことです。
例えば、10坪の土地に3階建てのアパートを建築し、7坪程度のワンルームの賃貸物件を3戸作れば、合計3戸の賃料を得ることができます。20坪の狭小アパートなら、7坪程度のワンルームの賃貸を1階ごとに2戸作り、2階建てでも合計4戸の賃料を得ることができます。
戸数や間取りなどは土地や地域の条件によって異なりますが、10坪~20坪の狭小地でも上記のようなアパートの建築・経営が可能です。
ただし、狭小地は整形地以外にも三角形や旗の形をした旗竿地など変形的な土地も多く、建築工事が難しい土地も少なくありません。このような変形的な土地でもアパート経営・建築は不可能ではありませんが、建築コストが高くなる傾向にあるので注意しましょう。
また、建築基準法や居住する地域の安全条例などの規制もあるため、望み通りのアパート経営ができない可能性も十分起こり得ます。
狭小地を所有するオーナーは、できるだけ希望に沿った形で経営ができるように、狭小地の建築に詳しいハウスメーカーや工務店に一度相談してみるのがおすすめです。
また、これから狭小地を購入してアパート経営を検討する方も、実際に狭小地の建築に詳しい専門家と一緒に土地選びをすると、設計や工事などもスムーズに進みます。

10坪・15坪・20坪の狭小地にアパートを建てることは可能ですが、狭小アパートには以下の3つの特徴があります。
東京都心部は、部屋の広さよりも利便性を優先する場合が多く、単身者などの需要が高まっています。また、早く入居してもらうためには、他のアパートとの差別化が必要になるでしょう。
まずは、10坪・15坪・20坪の狭小地のアパートの特徴について詳しく解説するので、狭小地のアパート経営を検討している方は参考にしてください。
狭小アパートは、都心部で需要が高くなっています。なぜなら都心部で生活する人は、単身赴任や学生など一人で住む人をはじめ、通勤や通学の利便性を求める人が多いためです。
最低限生活できるスペースとトイレやシャワーなど、必要な設備があれば狭くてもいいという単身者が多く、1部屋が4畳程度と狭くてもニーズがあります。都心部やオフィス街、駅やバス停から徒歩で10分圏内の場所など、立地が良ければ狭小地でも十分にアパート経営が可能です。
東京都心以外も、大阪・名古屋・福岡などの大都市の好立地では、狭小アパートの需要が高いです。近くに大学や大手企業などがある場所なら、大学生や会社員などの一人暮らしの需要も見込めるため、地域の調査とターゲットに合った間取りなどの設計が重要となるでしょう。
狭小アパートは、坪単価が高くなるのが特徴です。理由としては、10坪・15坪・20坪程度の狭小地は2階・3階建ての物件になる場合が多く、建物の建築費用が高くなる傾向があるためです。
坪単価とは、1坪(約3.3㎡)あたりの建築費のことを指すため、敷地面積が狭い狭小地は必然的に平米単価や坪単価が高くなります。
また、坪単価は建物の構造によっても変化します。木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造(RC造)・鉄筋鉄骨コンクリート造(SRC造)などによって建築費用が変わり、強度が高くなるにつれて坪単価が高くなるのが特徴です。
狭小地の土地活用においては、坪単価を意識して構造を選択し、収益性があるかどうかを検討しましょう。
狭小地のアパート経営を成功させるためには、他のアパートとの差別化が必要になります。なぜなら利便性や家賃などが同条件のアパートと狭小アパートを比較した際に、わざわざ狭小アパートを選択する人は少ないと考えられるためです。
特に三角形や台形などの変形的な狭小地は、家具の配置など生活する際に住みにくいと感じる場合も多いです。そのため、入居者にとって狭いという状況よりも、魅力的な付加価値を付ける必要があります。
入居者にとって魅力的な付加価値とは、以下のような例が挙げられます。
上記のように、ターゲットとする入居者のニーズに合った付加価値を取り入れることが大切です。例えば大学やオフィス街が近いエリアでは、無料インターネット環境の整備、急な転勤などに対応できる家具家電付きなどの物件の需要があることが予想されます。
また、ペットを飼っている人向けの物件なら、鳴き声や物音が気にならないように防音設備や遮音設備が備わっていると魅力的です。
ただし、様々な付加価値を付けてしまうと、本来のターゲットのデメリットとなってしまう可能性もあるため、専門家に相談しながら付加価値について検討するのがおすすめです。

狭小地でアパート経営をすると、以下の3つのメリットがあります。
狭小地のアパート経営は「土地小さいから収益が期待できないのでは?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。しかし、狭小地は土地が狭い分、土地代や税金が安いなどのメリットも多いです。
以下で3つのメリットについて詳しく解説するので、狭小地のアパート経営について迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
狭小地の土地は、土地面積が狭いので土地代が安くなります。土地代は面積が狭いほど安いため、狭小地を選択すれば、土地の購入費用を抑えることができます。
10坪・15坪・20坪の狭小地は広い土地を活用するより、建築の規模も小さくなるため、比較的ローコストで始められるのもメリットです。
ただし、狭小地は狭いが故に工事がしにくく、余計なコストがかかる場合もあり、建築費用が割高になるケースも多いのが難点になります。
一口に狭小地といっても、形状や需要、周りの建物や道路などの環境によっても状況が変わります。したがって土地代や建築費などの初期費用やランニングコスト、実際運用した際にどの程度の利回りになるのかなどをしっかりと調査し、事前に計画を立てることが大切です。
狭小地は、固定資産税や都市計画税なども安いのがメリットです。なぜなら狭小地の土地は広い土地よりも面積が小さいので、資産価値が低く課税額が安くなるためです。
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日に所有している建物や土地に対して課税されるもので、毎年納税しなければならない税金です。
さらに狭小地にアパートを建設し、小規模住宅用地の適用を受けることができれば、固定資産税および都市計画税の評価額を更に減額可能です。狭小地で上手くアパート経営ができれば、安定的な収入を得ることができ、その収益から固定資産税や都市計画税などの支払いに充てられるようになるでしょう。
狭小地は、駅から徒歩10分圏内など立地が良い賃貸物件は、狭くても家賃を高めに設定できます。理由としては、都心部では部屋の広さより利便性を求める人が多いため、家賃を高く設定しても需要があるからです。
また、土地の面積が小さい分、土地の購入費用や毎年支払う固定資産税や都市計画税なども安くなります。そのため、比較的コストが抑えられ、安定的にまとまった収入を得られるため、上手く行けばローリスクハイリターンの土地活用が行える可能性があります。

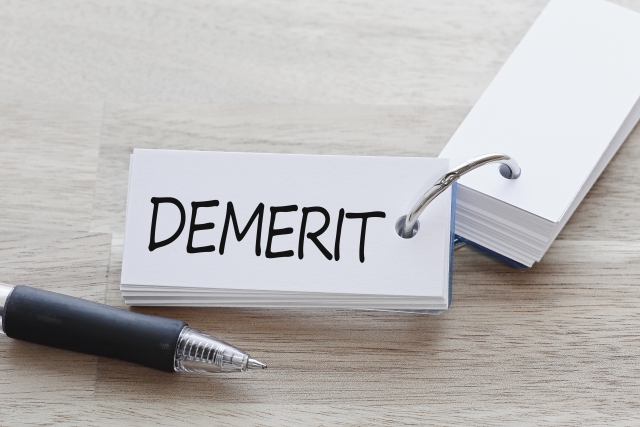
10坪・15坪・20坪の狭小地のアパート経営は、土地代や税金などのコストが安く済むといった魅力的なメリットも多いですが、デメリットも存在します。
狭小地のアパート経営のデメリットは、以下の3つが挙げられます。
狭小地のアパート経営は、周辺の道路や建物の環境などによって建築費が高額になる可能性が高いです。また、入居者が入れ替わりやすいという特性もあるため、空室などのリスクも考慮した上で利回りを計算するなど、前もってあらゆるリスクを想定しておくことが重要になります。
ここからは、狭小地のアパート経営のデメリットについて詳しく解説します。狭小アパートの経営を成功させるためにも、必ずチェックしてください。
狭小地にアパートを建てる際は、建築費が高くなる傾向にあります。なぜなら狭小地は土地の形状が変形的な場合が多く、基本的には注文住宅となるため、設計や施行にかかる費用が高額になるからです。
また、狭小地のアパートの戸数を増やすためには、建物を2階・3階と階層を追加して設計しなければいけません。階層を増やすと設計上、鉄筋コンクリート造や鉄骨造にしなければならないため、高額なコストがかかってしまうのです。
さらに狭い土地の周辺の建物との間や道路が狭いと、クレーンなどで資材を運ばなければならない場合もあります。したがって運搬料の追加や作業員の増員、特注品などの用意にもコストがかかる可能性があるのです。
上記のような理由から、狭小地にアパートを建設する際は土地代や税金が安いとはいえ、通常よりも建築費の予算を多く見積もっておくことが大切です。
また、高層階のアパートの場合、階層を増やせば床面積も増えるため、課税される税金も高くなることも理解しておきましょう。狭小アパートの経営は、費用対効果を十分に検討した上で、有効な方法を選択する必要があります。
狭小地のアパートの建築や経営について経験のない人が自己判断すると、失敗するリスクもあるため注意しましょう。工務店やハウスメーカー選びも慎重に行い、より現実的な提案をしてくれる専門家を選ぶことが大切です。
狭小地のアパートの建築は、施行期間が長くなる傾向にあるのもデメリットです。理由としては土地が狭いことで工事の際に重機などが停められない、建材を保管するスペースがないという問題があり、工事がスムーズに進みにくいからです。
そのため、狭小地にアパートを建設する際は、別に建材や資材の保管場所を確保したり、特注品の資材の用意をしたりなどの準備期間が必要になります。別の場所に保管スペースが確保できても、何度も運搬する必要があり、それなりの人手とコストの負担がかかります。
加えて、施行期間が長いとその間賃料を得ることができないため、すぐに収益化できないのもデメリットです。狭小地のアパート建設は、オーナーの建築コストの負担も大きくなるため、専門家などに相談しつつ費用体効果について慎重に判断しましょう。
狭小地のアパートは、入居者が入れ替わりやすい可能性があります。そもそも狭小アパートは、学生や単身赴任者などをターゲットにする場合が多く、環境や時期によって入居者の入れ替わりが頻繁に起こります。
例えば、大学生の場合は卒業と就職のタイミングでの引っ越し、社会人では異動や昇給による引っ越しなどが考えられます。契約者が退去することが分かったら、早めに入居者を募集する準備を始めましょう。
また、利便性だけを優先して狭小アパートに入居した方は、実際に生活してみると狭くて不便に感じてしまい、短期間で引っ越しを希望する方も少なからずいるのも特徴的です。入居者が変わりやすいということは、その間の空室の期間が長くなるリスクもあるため、一時的に収入が減る可能性があることを理解しておきましょう。
さらに、退去が多いとルームクリーニングの費用も頻繁に発生するため、契約時にルームクリーニング代の負担などについて取り決めをしておきましょう。

狭小地でもさまざまな土地活用が可能です。初期投資を抑えたい方や、リスクを分散したい方にとって、アパート経営以外の選択肢を知っておくことは重要です。
アパート経営以外におすすめな狭小地の土地活用方法は、以下の5つです。
ご自身の土地やライフプランに合った活用方法を探すヒントにしてください。
コインパーキング経営は、狭小地活用の中でも特に人気の高い方法です。建物を建てる必要がないため、限られた敷地でも有効活用しやすい点がメリットです。
コインパーキングは駐車時間に応じて料金を支払う仕組みで、誰でも契約不要で利用できる手軽さが特徴といえます。人や車の往来が多い立地では需要が高く、安定した収益が期待できます。
初期投資が少なく済むのも大きな魅力です。アパートやマンションと違い建設コストがかからず、一括借り上げ方式を選べば初期費用ゼロで始められる場合もあります。また、運営が比較的シンプルで、建物の老朽化リスクや修繕コストが少ないのも安心材料です。
さらに、将来的に土地を別の用途に転用する際にも対応しやすく、設備を撤去するだけで更地に戻せるため、柔軟な土地活用が可能です。
以下の記事ではコインパーキング経営で土地活用を行うメリットやデメリットについて詳しく解説しています。興味のある方は併せて参考にしてみてください。
トランクルーム経営も狭小地を活かせる有力な土地活用方法です。コンテナやビルの空きスペースを利用して収納スペースを貸し出すビジネスモデルで、近年注目が集まっています。
初期投資を抑えられ運営コストも少ないため、比較的低リスクで安定した収益が見込めます。アパートやマンションのように居住者対応や修繕負担が大きくないため、管理の煩雑さを避けたいオーナーにも向いています。
初期投資は200万〜800万円程度と比較的少額で始められ、土地の形状に左右されにくいのもメリット。いびつな形の土地や住宅には向かない立地でも収益化できる可能性があります。
ただし、賃貸住宅に比べて収益性が低いケースもあり、近年は競合も増えています。そのため、立地調査をしっかり行い、差別化できるサービスを検討することが成功のカギとなるでしょう。
以下の記事ではトランクルーム経営のメリットやデメリットについて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
レンタルスペース経営は、狭小地でも効率的に収益化を目指せる注目の土地活用方法です。オフィス、会議室、イベントスペースなどを時間単位で貸し出す仕組みで、近年利用者が増加しています。
レンタルスペースは一般的な賃貸借契約に比べて運営手続きが簡単なうえ、多様なニーズを取り込みやすいことが利点です。アパート経営と比べて初期投資も抑えられるため、比較的低リスクでスタートできる点も魅力の一つです。
レンタルスペースには多彩な種類があり、土地の形状や広さ、地域性に合わせて柔軟に設計できます。以下は、主なレンタルスペースの種類をまとめた表です。
| 種類 | 主な用途・特徴 |
|---|---|
| レンタルオフィス | デスクや椅子、ネット環境が整い、個人事業主やフリーランスが自宅外で仕事をするために利用される。 |
| パーティー向けスペース | 誕生日会や懇親会などのイベント用。テーブルや音響設備が整い、手軽にパーティーを開催できる。 |
| 会議室 | ビジネスミーティングやセミナー向け。プロジェクターやホワイトボードがあり、集中した会議に適している。 |
| スタジオスペース | 撮影、ダンス、音楽の練習などに利用され、広いフロアや専門設備が備わっていることが多い。 |
| ブーススペース | 小規模イベントや展示会用の個別スペース。特定のテーマや商品の紹介に適している。 |
これらのタイプは、狭小地でも効率よく収益を生み出せる点で特に注目されています。自動化された予約管理システムを導入すれば無人運営も可能で、管理の手間を大幅に軽減することも可能です。
一方で、競合が多い分野であるため差別化は必須です。また、建築基準法や消防法、用途変更の有無など法規制の確認も欠かせません。
戸建て賃貸経営もアパート経営以外の有力な選択肢です。
戸建て賃貸経営とは、一戸建て住宅を賃貸物件として貸し出し、家賃収入を得る方法です。アパートやマンションに比べ戸建て物件の供給が少なく、賃料の値下げ競争に巻き込まれにくいといった特徴があります。さらに、戸建ての建築費は平均で約2,000万円程度と、アパート経営より初期投資を抑えやすく、リスク軽減にもつながります。
ファミリー層を入居者に想定すると、子どもの転校を避けたいというニーズから長期入居が期待でき、安定した家賃収入を得やすいのもポイントです。
一方で、アパート経営ほどの高い収益性は見込めず、空室が発生すると収入が途絶えてしまうリスクもあります。自主管理を行う場合、入居者対応やトラブル解決の手間が増えるため、管理会社への委託を検討するのも一つの方法です。
戸建て賃貸経営は、競合が少ない分、安定した収入が見込める土地活用法です。成功には地域の需要をしっかり調査し、入居者ニーズに応じた物件づくりと管理体制の構築が不可欠です。専門の不動産会社への相談もおすすめです。
以下の記事では戸建て賃貸経営の具体的なメリットやデメリットについて解説しています。併せて参考にしてみてください。
賃貸併用住宅は、自宅に住みながら家賃収入を得られる、狭小地活用の中でも注目度の高い方法です。住宅ローンの負担を軽減しつつ、自分の住まいをしっかり確保できる点が大きな魅力といえるでしょう。
賃貸併用住宅とは、戸建て住宅の一部を賃貸スペースとして活用する形態を指します。例えば1階を賃貸部分、2階を自宅として使うケースが一般的です。賃貸部分から得られる家賃収入を住宅ローンの返済に充てられるため、資金計画を立てやすく、経済的な負担を軽減できます。
また、自宅部分が全体の50%以上を占めれば住宅ローンの利用が可能で、低金利で融資を受けられる点もメリットです。さらに、賃貸併用住宅は相続税対策としても有効です。賃貸部分の評価額が自宅部分より低くなるため、相続税の負担を抑えられる可能性があり、固定資産税の特例措置を利用できる場合もあります。
一方で、賃貸併用住宅には注意点も存在します。自宅と賃貸部分が同じ建物内にあるため、生活音やプライバシーの問題が生じやすくなります。また、賃貸部分を設けることで設計に制約が出たり、空室が発生すると収入が減少したりするリスクもあります。さらに、賃貸部分の管理や入居者対応の手間がかかる点も理解しておく必要があるでしょう。

狭小地を活かして収益化するためには、以下3つのポイントを押さえることが重要です。
順に解説します。
狭小地の収益化を目指すなら、土地にかかる法的制限や条件をしっかり把握することが重要です。
用途地域によって建てられる建物の種類や用途が制限されているため、計画が頓挫しないよう事前確認は必須です。例えば、商業地域なら店舗が建てられますが、住居専用地域では原則住宅以外の建築は認められません。
また、容積率や建ぺい率といった建物の規模に関わる制限も狭小地では大きな影響を与えます。これらの数値が小さいと建築可能な床面積や建物の占有面積が制限されるため、慎重な設計が求められます。
さらに、接道義務(幅4メートル以上の道路に敷地が2m以上接していること)を満たしていないと建築が認められない場合があるので、土地の形状や周囲の環境も確認しましょう。
防火地域や準防火地域の指定がある場合は、建物の構造や使用材料に厳しい基準が設けられることも覚えておきたいポイントです。加えて、景観法や土砂災害防止法など、都市計画法や建築基準法以外の法令も関係してくるため、総合的に調査を行いましょう。
収益化を安定させるには、土地の立地と周辺のニーズに合致した活用方法を選ぶことが重要です。
交通アクセスの良さは特に重視すべきポイントで、駅やバス停が近い場所は賃貸住宅や駐車場、コインランドリーの需要が高まります。都市部では特に交通の便が入居者の選択に大きく影響します。
地域特性の理解も欠かせません。観光地近くならコインパーキング、ビジネス街ならレンタルスペースが適しています。
市場調査を行い、人口動態やライフスタイル、競合状況を把握することも成功の秘訣です。例えば、共働き世帯が多い地域ではコインランドリーやトランクルームの需要が増す傾向にあり、土地活用の具体的な方向性が見えてきます。
狭小地の活用には特有の制限や課題が多く、限られた土地を最大限に活かすには信頼できる専門業者のサポートが欠かせません。豊富な知識と経験を持つ業者なら、地域の特性や市場の動向を踏まえて最適なプランを提案してくれます。
専門家に相談することで、法的制限や地域ニーズに応じた効果的な対策が可能です。さらに、限られたスペースを効率的に活用し、初期投資や運営コストを抑える工夫も得られるため、収益性の向上にもつながります。
東京都内の狭小地の土地活用でお悩みの方は、ぜひM-LINEへご相談ください。土地の条件やご希望に合わせて、オーダーメイドの最適な活用方法をご提案いたします。土地活用に関するあらゆる課題や税金、固定資産税の問題についても、専門スタッフによる丁寧なコンサルティングで解決をサポートいたします。


今回は、10坪・15坪・20坪の狭小地でアパート建築・経営ができるのかについて詳しく解説しました。狭小アパートは、都心部などの好立地の場所では需要が高く、利便性を求める方に人気のある物件です。
そのため、狭小地でも十分にアパート経営は可能ですが、建築費が高額になったり、施行期間が長くなったりとデメリットもあるため注意が必要です。10坪・15坪・20坪の狭小地にアパートを建てたいと考えている方は、費用対効果を考え、設計や間取りなどを慎重に検討する必要があります。
M-LINEでは、狭小アパートを検討している方に「マルチ・スカイ・アパートメント」をおすすめしています。マルチ・スカイ・アパートメントとは、鉄筋コンクリート造のアパートで、1cmも無駄にしない家づくりが実現できます。
土地の形状・建ぺい率・容積率・土地面積・地形・地盤・道路付けなど様々な規制や状況に柔軟に対応でき、1cmピッチの完全自由設計を採用しています。
M-LINEでは、横の面積だけでなく、縦の面積も調整することができる大手ハウスメーカーよりも1層高い建物や、傾斜建設などの提案が可能です。「他社で断られた」「要望の戸数が実現できなかった」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。